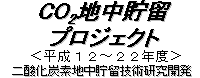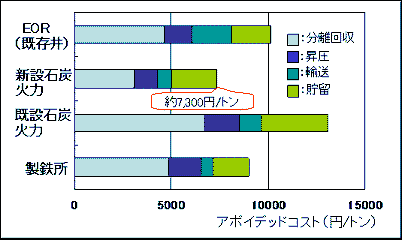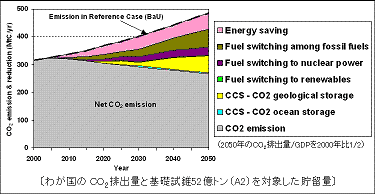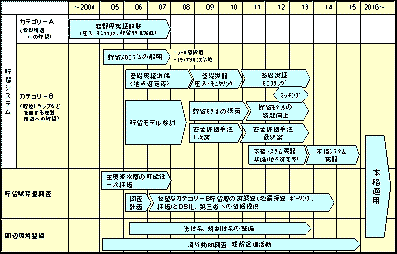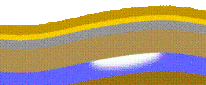|
|
 |
有効性評価
 目的 目的
CO2地中貯留の様々な技術的課題を解決し、その有効性を明らかにするため、以下の項目を実施しました。
 コスト評価 コスト評価
CO2地中貯留システムを類型化し、想定モデル地点調査における実規模での仮想的な圧入計画を基に、コスト分析を行いました。その結果、現状技術による地中貯留コストはトン当たり7,000円から15,000円であることが想定されます。
想定モデル地点調査等に基づくコスト分析例
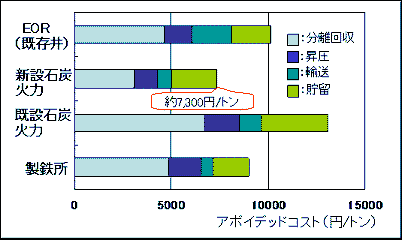
| 標準条件 |
回収隔離量100万トン/年(除くEOR)、輸送距離20km、昇圧10MPa、圧入法ERD、坑井1本当たり圧入量10万トン/年 |
| 石炭火力(共通) |
電気代5円/kWh、既設石炭火力:補助ボイラ設置による蒸気供給 |
| 製鉄所 |
蒸気2,500円/トン、電気代10円/kWh、EOR:新設石炭火力から20万トン/年分離回収 |
海外でのコストと比較すると、輸送コスト、貯留コストが際立って高いという結果が得られました。輸送コストについては、人口密集地の多い地点を通過する我が国では、高くなります。貯留コストについては、我が国では浸透率が海外に比べて低く、坑井1本当たり圧入できる量が限られているため高くなります。
海外との地中貯留コストの比較
| |
国内の現状
円/t-CO2 |
IPCC SRCCS
US$/t-CO2 |
| ケース |
新設石炭火力
〜帯水層貯留 |
新設石炭火力
〜帯水層貯留 |
新設NGCC
〜帯水層貯留 |
新設石炭火力
〜EOR |
分離回収
〜昇圧 |
4,200 |
29 - 51 |
37 - 74 |
29 - 51 |
| 輸送 |
800
100万t/y - 20 km |
1 - 8
500 - 4000万t/y - 250 km |
| 圧入 |
2,300
10万t/y・well, ERD |
0.5 - 8 |
Δ10 - 16 |
| 合計 |
7,300
100万t/y - 20 km, ERD |
30 - 70 |
40 - 90 |
9 - 44 |
以上の検討結果を踏まえ、実適用に向けて取り組むべき課題として以下のものが挙げられます。
|
|
| 全体コストの6割以上を占める分離回収工程のコストダウン |
|
|
|
| 輸送コストが海外に比べて高いことから、排出源近傍の貯留層を利用 |
|
 総合経済性評価 総合経済性評価
CO2地中貯留の総合経済性評価では、数理計画モデルを構築し、想定モデル地点調査のコスト分析および貯留可能量調査を実施しました。
日本の地中貯留のコストは海外コストよりも割高ですが、再生可能エネルギーのポテンシャルも限定されており、省エネについてもかなりのレベルが既に達成されているため、安価で大量にCO2を削減できるオプションは限られています。したがって、地中貯留は海外よりも多少割高であっても、全体的な対策の中で相対的に安価であり、地中貯留の役割は大きいことが定量的に示されました。
また、基礎試錐データのある52億トン(A2)の貯留層を対象とする試算では、2050年のGDP当たりCO2排出量を2004年比で1/2とする目標を立てた場合、約半分程度が経済性を有する可能性があることが示されました。これによって、今後の利用貯留層が拡大されることにより、経済性を有する貯留量は極めて大きくなると想定されます。
 ロードマップ ロードマップ
有効性評価では、CO2地中貯留の様々な有効性シナリオをもとに海外動向も考慮し、地中貯留の本格実施を平成27年度と設定して、今後必要な課題の抽出とロードマップを作成しました。これは、ロードマップを作成することにより、今後の技術開発、普及の道筋を明確化し、大規模排出源等を有する関連企業等の地中貯留への理解を促進するねらいを持っています。
地中貯留の実適用に向けては、コストの低減が重要です。大きな割合を占める分離回収コストの削減を図るとともに、排出源と貯留層との距離等を考慮して、輸送コストを大幅に低減させることも重要な方策となります。このため、排出源近傍の沿岸域に広く分布するカテゴリーBの帯水層を対象とした技術的な貯留の可能性を基礎実証試験とそれに基づく貯留モデルの構築を図る必要があります。また、それらに併せて、排出源近傍の沿岸域貯留層賦存量調査、地中貯留に対する理解促進活動も併せて進めていく必要があります。
ロードマップ
(出典:経済産業省産業技術局資料「CCS2020」)
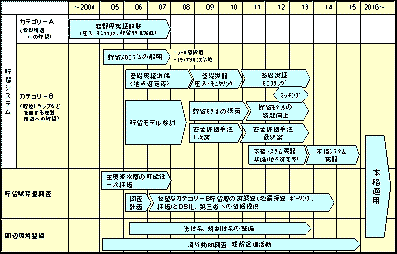
クリックで拡大
 成果 成果
|
|
| 現状技術による地中貯留コストはトン当たり7,000円から15,000円であることが明らかになり、取り組むべき課題を抽出しました。 |
|
|
|
| 地中貯留は相対的に安価であり、今後の利用貯留層が拡大されることにより経済性を有する貯留量は大きくなると想定されました。 |
|
|
|
| 平成27年の本格適用を念頭においたロードマップを提示しました。 |
|
 今後の課題 今後の課題
|
|
| コスト分析や貯留可能量調査の進展、国内外の動向などに基づく、CO2地中貯留の様々な有効性シナリオやロードマップの精度を向上させます。 |
|
|
 |